第二部 敗残
玉砕
陸軍の内、五十連隊は酷寒の満州遼陽よりの派兵、百三十五連隊にしても寒冷の地から常夏の島に移されたのは良いとしても、広大な戦場に馴れた者が四方を海に囲まれた小さな島を戦闘の場所とするには戸惑いも多かっただろう。我々海軍は常に狭い艦船内での戦闘を想定しており、テニアン島はまさに浮沈空母として頼もしい限りであった。しかし玉砕という過酷な運命はそのような互いの特性の違いも容赦無く飲込んでいく。
昭和十九年七月三十一日午後、テニアン島カロリナス台南端に於いて海軍警備隊大家司令以下の突撃。続いて陸軍残存兵の突撃。同年八月一日から三日にかけて海軍航空隊角田中将以下の敵戦車群への突撃。
組織だった日本軍の反攻はこれを最後とし、日本軍はテニアン島から消滅した。
私は司令部洞窟付近にいた海軍の中尉位の士官の指揮下に入り、大家司令を先頭に米戦車に突撃した。玉砕突撃した約四百名中、不幸にして生き残った者二名のみ。
高野少年兵
玉砕突撃にも生き残ってしまった私は司令部洞窟に戻り、中にあったドラム缶の水を腹一杯飲み、少し落ち着くと、『大した手柄も立てずに、このまま死ぬのは残念』と思い、もう少し様子を見ることにした。元の司令部の兵員が便所に使っていた少し下の横穴に、大人三人がやっと居られるようなでこぼこの横穴を見つけ入り込んだ。
数日経ったある日の深夜、その便所の周りを人間がちょろちょろと何かを探している様子。米軍にしては動きが少し違うようだ。自決用の手榴弾の安全栓を抜き、発火させるため打ちつけようとしてから、日本軍の合い言葉、「必勝、」と言うと、その者はハッとしながら、「神念、」と応えが返ってきた。「日本軍か、」「そうだ、」と言って近付いて来た。よく見ると少年兵らしい。
その少年兵は敵弾で肺を後ろから貫通され、耳は彼の居た洞窟が米軍に爆破されため聞こえ難い様子で、司令部洞窟には短剣を探しに来たということだった。死に損ないの少年兵にしては、私よりも立派と感心した。
永田氏の戦死
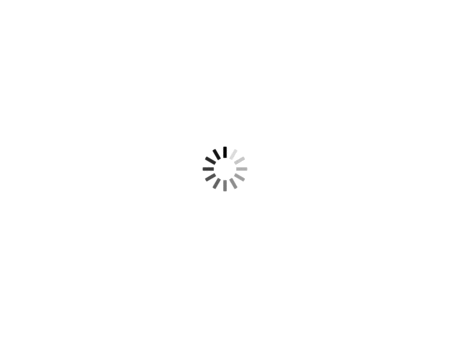
それから共に敗残生活をする事になったこの少年兵が高野(現姓森岡)利衛氏であった。
時を同じくして、私達の洞窟に、背後から機関銃弾を受けて虫の息のような兵が横たわっていた。背骨で弾が止まっている様子であったが、刃物も無く手術など出来そうもなかったため、只見守るだけであった。二日ほど過ぎ、その人は本当に静かな声で、「私は横浜の永田という者です。家の裏の高台へ登ると港がよく見えました。」と言い、少ししかない水を飲ませると静かに息を引き取った。この時は昼間に米軍が洞窟に入って来て、ドラム缶の水を下の便所に皆あけてしまったため、最後の水もほんの一、二滴しか無かったのだ。
暑いテニアンで永田さんの遺体はすぐに腐乱し始め、夜になると横になっている我々の鼻の穴に出入りするうじ虫に悩まされた。しかし、『我々にも何時かはこの永田さんと同じ運命が待っているのだ。』と自分に言い聞かせると心も落ち着き、うじ虫も気にならなくなってきた。
そうして一ヶ月近くも経った頃、数名の米兵が毎日洞窟へ金ばしごで下りてきて、司令達の居た所にあった道具や、突撃の際ハンマーで破壊していった無電機等をいじくり回していくようになった。米軍上陸部隊の交代があったようである。 この場所は灯台元暗しとはいえ、米軍部隊の最前線であり、一発のダイナマイトか火炎放射器で焼き払われれば一巻の終わりである。米軍が我々を発見するのは時間の問題であった。
『この洞窟も今晩が最後だ。永田さんと別れよう。』
今日までは、デンデンムシ(カタツムリ)を十匹位とると、白骨となっていた永田さんに先に供えて手を合わせ、細いサツマイモを一本か二本掘ると、先に永田さんに上げて手を合わせる。毎日欠かさず続けてきた。詫びしいながらも我々に出来る精一杯のこの供養も今夜が最後だ。『永田さん、さようなら。すぐ後から行くから。』と二人で心の中で告げ、深夜に司令部洞窟を出た。
その後、第二回目の慰霊団にてテニアンに渡った時、永田様の御遺骨はやっと内地に帰ることが出来、厚生省により墓地に埋葬された。私と森岡氏も同席しました。
ジャングル
最後の集結地カロリナスに於ける日本軍の夜のみの散発的な抵抗も次第に下火になり、銃声も遠のいた昭和二十年の二月頃かと思われる頃、我々は東海岸の断崖の下のジャングルに分け入った。この時から数カ月に及ぶ敗残兵生活が始まる。
我々は軍人なのだ。捕虜になるわけにはいかない。今となっては生きられるだけ生き抜くしかないと覚悟を決めた。昼は米軍の銃口を逃れて洞窟や岩陰に身を潜め、夜になるのを待って食糧や水を探してジャングルを徘徊する。
ジャングルの中には所々に民間の人達が住んでいたような場所が何カ所もあり、彼らが置いて行ったらしいタピオカという芋のような物から作った粉が少々残っており、それを頂いて空腹を充たす。
ジャングルを中腰でしばらく歩く。と、頭に何か当たった。見ると目の前に足が揺れているではないか。見上げると男が木の枝にヒモを掛け、首を吊っている。民間の男性らしい、死亡して相当時間が経っているようだ。この男の家族はどうしたのだろう。無事に米軍に助けられただろうか。気がつくと私の頭から血が滴っている。銃弾で負傷し、やっと張った薄皮を彼の足先が蹴破ったらしい。
ある日の未明、カロリナスの崖下を東海岸に向かってジャングルを掻き分けているとすぐ頭の上で声がする。急いで崖の窪みに背を押しつけて息を殺す。手を伸ばせば届くような所に足が見える。米軍の歩兵らしい。黒光りする自動小銃を崖下に向けて立っているではないか。我々には気づいていない。その時、先方のジャングルで誰かがガサッと音を立ててしまった。米兵がすかさず手榴弾を投げた。轟音がジャングルを揺るがす。しかし誰もやられた様子は無い。米軍の歩兵らしい者がまた近くに集まって来たらしい。しばらく息を殺して米兵が帰るのを待った。
夜になるのを待って再びジャングルをバンザイ岬に向かって歩きだしたが、またもや首吊り死体にぶつかった。この人も民間人だ。何とこのジャングルは墓場のようだ。戦場になる前はここにも相当数の民間人がいたらしい。方々に生活の跡が見える。こんな場所にも人々が住んでいたのだろうかと驚く。我々軍人は常に戦場を往来していたため、このカロリナス台下のジャングルに入るのは初めてであった。
合流
十月上旬であったと思う。カロリナスの司令部洞窟より断崖を降り、海岸下の洞窟を見つけた。その洞窟には五、六名の兵士がいた。ほとんどが海兵で、警備隊の生存者にも芳賀隊の今井兵曹(生還)、二本ヤシ柴田砲台の生き残りの藤田兵曹(生還)、中村先任伍長、清水一水がいた。清水一水は極度の栄養不良で歩くことは勿論、生きているのがやっとの状態だった。合流した我々は毎日、夜を待って海岸の上に出て食料を探し歩いた。そうしたある夜、海岸の波打ち際をぼろ切れのみの姿で、海を泳ぎ岸に上がって、南海岸から東海岸の方へ歩いてくる敗残兵がいるではないか。近寄ってよく見ると、なんと警備隊小川砲台の先任下士官、中村上曹ではないか。また敗残兵が一人増え、心強いやら心配やら複雑な気分になった。
やがてこの洞窟も去らねばならぬことになった。二人連れで海岸を歩いてきた米兵を洞窟の中から射殺してしまったのだ。連れの米兵は一目散に逃げ帰った。それからが大変だった。我々の洞窟の上に目印を立て、海からは駆逐艦で艦砲射撃の準備をし、頭上ではディーゼルエンジンのドリルで穴を開けて爆破しようとしているのだ。
この穴も今晩限りだ。よし、今晩中に海岸を上がろう。しかし、海岸の上には米軍の歩哨が立っているのだ。海岸の洞窟から一人ずつ、上を注意しながら少しずつ登り始めた。仲間の一人は泳ぎが達者らしく、海へ飛び込んで泳ぎ始めたが、なかなか岸より遠くへ離れて行くことが出来ず、行きつ戻りつしていたが、やっと大波に乗って手を振りながら波間に見えなくなった。目の前の海上四キロ南に、無人島アギーガン島(ヤギ島)が黒く横たわっている。アギーガン島に辿り着く前に、大鮫に出くわしてしまったのか、生存者名簿にはついに見つからなかった。我々は禄なものを喰っていず、体も弱っている者が多いので、海岸の上を強行突破して米軍に狙撃されても誰かは残るだろう位の考えで、少しずつ登り始めた。私は一番か二番目位に、米兵が海上を見ているすきに足元数メートルのところを通り抜け、カロリナスの崖を目指して一目散に走った。すかさず米兵が発見し銃を乱射したが、幸いなことに夜の銃弾はなかなか命中しない。やっとカロリナスの崖下のリーフの岩の割れ目に身を隠し、少しずつ移動してマルポーの海岸へ向かった。
敗残兵
米軍の敗残兵掃討は日毎に激しくなり、カロリナスの台上にも台下にも米軍の歩兵部隊が朝から行動するようになっていた。点在する洞窟と焼け残ったカロリナスのジャングルを火炎放射機で焼き払い、手榴弾で爆破して歩くのだ。私と高野、清水の三人は追い詰められて次第に身を隠す場所に窮し、相談の結果、一緒に居るよりもバラバラに行動した方が米軍に発見され難いだろうとなった。
我々は別々に焼け残った砂糖黍畑に潜伏し、二日間はなんとか無事に過ごすことが出来た。しかし三日目になると砂糖黍畑が燃えだした。米軍が火を付けたのだ。最初の内、米軍は無益な殺生をする気は無く、投降を待っていたらしいが、油断をすると何処からともなく手榴弾一つで体ごと突っ込んで来る日本兵に手こずり、焼き払い戦法に出たらしい。風上に火を付け、風下に出てくるところを機関銃隊が皆殺しにするのだ。
私は砂糖黍畑の低いところに身を伏せ、熱いのを我慢して火勢の衰えるのを待った。やがて頃合を見計らって移動しようとするとバリバリと大きな音が聞こえてきた。なんと米軍の戦車が風上から砂糖黍畑を踏み潰しながら迫って来たのだ。もうこれまでと覚悟を決めた。ところが戦車は私が身を伏せている六、七米横を通り過ぎて行くではないか。あのまま真っ直ぐに来られたら間違いなく踏み潰されていただろう。どうして避けていったのかと不審に思ったのは後のこと、その時は安堵の思いで溜息を吐くのが精一杯だった。私の前方二、三米の処に砂糖黍運搬用に使用していたトロッコの線路があり、戦車はそれを避けて行ってしまったのだ。高野も私同様の好運で殺られずにいた。日が暮れるのを待って他の隠れ家を探す事になった。
あまり暗くならない内に行動しなければならない。米軍が帰るとすぐに移動を始め、足元に気を付けながら洞窟を探した。どうやら米軍の最前線の近くでは安全な場所など有る筈も無いと気が付いた。高野と二人で顔を合わせ、無事を喜んだのだが、今日は無事でも明日はわからない。今晩だけはどこかに身を隠し、明日は米軍の前線を突破し、敵中奥深い場所の方が米軍が油断して却って安全だろうと言うことになった。
夜半前に出発した。マルポー水源地付近を通り、道路を避けて歩いて十字路に出た。米軍の歩哨を警戒して十字路の手前でリーフのかけらを五、六個拾い、前方に投げた。もし歩哨が居れば彼等は口笛を吹くか、小銃を一発か二発、空に向けて発砲して味方に知らせるのだ。もっとも風下から近付けば米兵の体臭や頭髪の臭いで五十米位前から気付くことが出来る。彼等がいれば遠く迂回して避ける。
野戦病院
ソンソン町の北の崖の中腹を音を立てぬように通過し、元の警備隊司令部洞窟の上を通り抜けたところで、野戦病院のあった洞窟に缶詰の箱が沢山あったのを思い出した。確か負傷者の寝ていたところの下にあったはずだ。その洞窟の近くまで行くと崖の下の方が真昼のように明るい。米軍の物資の集積所らしい。煌々と電灯を点け、自動小銃を肩に掛けた歩哨が積み上げた物資の周りを警戒している。我々から二、三十米の近さであった。息を殺して岩陰に潜み、暫く様子を伺っていると、歩哨が遠ざかって行くのが見えた。「今だ、」静かにそこを離れ、洞窟に向かった。
野戦病院跡に着くとそこには既に米軍が入っていた。戦死者は運び出され、缶詰の箱は外に持ち出して殆ど焼却してあった。焼けただれた缶詰の中から何とか食べられそうなのを幾つか選び出し、持ち帰ることにした。また歩哨の目をかすめてペペノゴル小川砲台方面へ向かった。広い道路に出た。この道路はもっと狭かった筈だが、米軍のトラックが踏み潰して広くなったらしい。この道路を横切らなければならないのだが、夜間にも拘らずトラックがひっきりなしに通っており、なかなか機会がつかめない。カーヒーやハゴイ方面へ輸送しているらしい。トラックの列の途切れる間を待ってやっと突切る事が出来た。
ペペノゴル
ペペノゴルへ近付くと多少ジャングルらしい処もあり、やや安心して歩くことが出来た。小川砲台はすぐに見つけられた。米艦隊との砲撃戦で命中弾を受けた杉本兵曹の二番砲は砲身が空を向いて使用不能となっており、銃丸のコンクリートも天井も艦砲と空爆によって無惨に崩れ落ちていた。高野と二人で大砲の打ち針(尾栓)を取り外して海へ投げ込んだが、今考えてみれば米軍がこんな旧式の大砲など使用する筈がないのに無益な事をしたものだと思っている。東の空の明星が大きく、明るくなってきた。夜が明けようとしている。急いで海岸近くの繁みに入り、息を殺して潜んでいた。
太陽が昇ってきて南洋の暑さが次第に身にこたえるようになってきた。我慢してじっと耐えていると、突然米兵の声がした。声のする方を伺うと、上半身裸の数人の兵が我々の潜んでいる直ぐ前の崖を降りている。海岸には砂浜があり、木製のボートが上げられているのが微かに見えた。彼等は昼日中、浜の浅瀬で舟遊びをしているのだ。そうだ、今夜あのボートを盗んで隣のヤギ島(アギーガン島)へ逃げよう。生きて日本へ返る心算はないが、無人島で一生を終えよう。そう考えて高野に目で合図した。彼も私の意図が解ったようだった。日が暮れるのを待って昼間米兵が昇り降りしていた崖を下り、砂浜のボートに近付くと所々にガスの火が見え、人の気配が感じられる。ハッと身構えるとパンパンと小銃か拳銃の発射音がした。我々は一目散に逃げ出し、元の崖の上に戻った。幸い誰にも当たらず、ホッと胸をなで下ろした。まさか米兵がまだ居るとは思わなかった。彼等は海水浴の後、冷えた体をガスの火で暖めていたらしい。彼等もさぞ驚いたことだろう。
後になって聞いた話だが、前夜か前々夜に数名の敗残兵が小舟を盗んで無事にヤギ島に着いたという。ヤギ島までの海は海流が早く、相当詳しい者でなければ辿り着くことは出来ないと言う話であった。彼等は無人島だと思って渡ったのだが、そこには陸軍の少隊か中隊程度の小数の兵員がおり、やっと辿り着いた彼等は敵前逃亡の罪で処刑されそうになったという。自分としても戦友が皆戦死しているのにヤギ島に脱出する事などよくも考えたものだと情けなく思った。
新湊
小舟を盗んでの脱出を断念し、新湊方面に向かった。昼間、海岸上の岩の割れ目に身を隠して海面を見ていた時、大きな海亀が数匹群れているのが見えた。『この海亀のように海で生きられたら良いなー』等と考えていると、今の敗残兵の生き様をつくづく情けなく思ったことか。
新湊では高野と一緒に米軍基地の近くに潜み、米兵との共同生活をしているような塩梅で過ごしていた。ある雨の降る夜、多分カーヒー付近だと思うが、だいぶ広い道路の左側を歩いていた。突然、何かに当たったような気配がしたと思ったら、「ギャーッ」とか「ノーッ」とか人間の声がした。日本兵の声ではない。「アッ」とこちらも驚いて一目散に逃げ出した。米兵が二、三人、頭から雨カッパを被り、箱に腰掛けていたのに突き当たってしまったのだ。米兵は大声を出して我々を追って来る。ここを先途と逃げるのだが、なにしろ奴等は脚が早い。足の長さが違うから当然の事である。この侭ではすぐ追い着かれると思い、道の左側の二番芽が出た砂糖黍畑に跳び込んだ。砂糖黍の狭い間隙を横歩きに逃げて道路から少し遠ざかった処で米兵に道路から手榴弾を投げ込まれた。私の側のリーフの小山に当たって爆発し、轟音と共にリーフの破片が飛んで来て腰の後ろに突き刺さった。細かい破片は自分で取れそうだったが、腰が痺れて痛かった。何とか我慢出来そうだと数刻そこにじっとしていた。
米兵は畑の中までは追って来ず、引き揚げて行ってしまった。この辺は米軍の飛行場の近くで、彼等は警備兵だったらしい。まさか足元に日本兵が潜んでいようとは思いもしなかったろうに、この時刻、この辺でばったり出喰わしたのだから彼等もさぞかし驚いたろう。
普段なら彼等の存在はすぐに気付いたのだが、急なスコールの中、頭から雨カッパをすっぽりと被っていたので、彼等特有の臭いが我々に届かず、突き当たるまで気が付かなかったのだ。
暫くそこにじっとしていたが、それ以上彼等の動きも無いようなので、畑の中を進むと高野達と出会った。殺られはしなかったかとお互いに心配していたが、また無事に再会することが出来た。何度も米兵に発見され、その度に命からがら逃げ延びることが出来た。今生きているのが不思議なくらいだ。
今日もまだ命はあったが、食料の確保が大変だった。デンデン虫と甘藷の葉とガマ蛙で何ヵ月生き延びたろう。最近では月日を数えるのは我々には意味がなかった。その日を生き延びるのが精一杯でそんな心の余裕はなかったのだ。自決用の手榴弾はまだ使えそうだが、今では自決は出来なくなっていた。情けない敗残兵の姿だった。本当に自分ながら情けないと毎日思っていた。
再びカロリナスへ
明日からこのテニアンのどの辺で生きようか、皆もその事を考えているようだった。誰の考えも皆同じだった。さあ、出発しよう、腰の痛みは大した事は無い。三人は歩き出した。誰の足も自然とカロリナスに向かっていた。皆が玉砕したカロリナスへ。死ぬならカロリナスだ。玉砕の地、カロリナス台上だ。カロリナスへ帰ろう。
カロリナス台上に着くと戦死者の遺体は見当たらなかった。玉砕後、二、三日の内に米軍が片付けてしまったらしい。またねぐら探しをしなければならない。その晩は二組に別れてジャングルに潜み、空き腹を抱えて一夜を過ごした。
夜が開けて太陽が高くなると米軍の黒トンボがやって来て我々の上をぐるぐると一時間ばかり偵察して帰る。観測機が我々の行動を監視しているのだ。機銃弾を御見舞いされない分、グラマン戦闘機よりはましなのだが、何とも気色の悪い黒トンボだ。
乾パン
黒トンボの姿が見えなくなると敗残兵が集まって今晩の食料探しの相談をする。我々は小川隊長の居た小川隊本部の防空壕を考えていた。その壕が見つかれば何か食料が残っている筈だと思い出していた。高野もそうだと相槌を打つ。夜になるのを待って早速出掛けた。確か三名で出掛けたと思う。
案外早くその壕は見つかったが、米軍の戦車砲で滅茶苦茶に潰されて原型を留めぬ程だった。壕の中は土砂で埋まり、肝腎の食料は何処に有るのかわからなくなっていた。それでも三人で手や板切れや棒などで懸命に掘ったが、仲々掘れるものでは無かった。途中、衣類などが出てきた。私は小川隊長や側近の兵達の自決体でも有ればとの思いもあり、一心に掘り下げた。しかし、夜明けが近くなってきたので、明晩また来ようとなり、掘った土を元に戻してその日は引き揚げた。
昼はジャングルにじっと身を潜め、夜を待って再び壕に戻り、昨晩の続きを始めた。昨晩堀った処までは土が柔らかく、容易に掘り進められた。時々米軍のトラックがマルポー方面からサバネタバシの手前を通り、カロリナス台に登って一巡して帰って行く。トラックのライトが我々の方を照射する度に身を伏せてやり過ごし、また掘り進めるのを何度か繰り返した。とうとう棒が何かの缶に当たった。金属製の箱が出てきた。良く見ると海軍の乾パンの入った箱ではないか。これには皆大喜びであった。この箱一つ有れば一人なら一ヵ月くらいは生きられる分量であった。小川隊長が我々に残して呉れたものと勝手に解釈して有り難く頂戴する事にした。しかし、四、五人の仲間でこれだけ食べているととても保たない。副食として野菜代わりにバナナの葉の芯を摘み採り、海水で揉んで食べた。甘藷の葉が有れば一番の野菜なのだが、なかなか見当たらなかった。
デンデン虫
そうこうして月日が過ぎていった。有る夜のこと、米軍の射撃練習場を見つけ、そこの番小屋に入って何か無いかと手当たり次第に品物を掻き回してしまった事が有った。朝になって米軍の知る所となって敗残兵の仕業とわかり、掃討の兵が繰り出されてきた。まさに薮蛇であったが、我々はそこまで追い詰められていた。
自動小銃で武装した米軍の歩兵は十名から二十名くらいが一組になり、一日中洞窟を掃討して歩いた。最近は米軍の方針が変わったらしく、米軍の兵舎とか陣地などを襲わなければ敗残兵討伐はあまり無くなって来ていた。
月日が過ぎて行き、相変わらず食料調達は侭ならなかった。デンデン虫は生ではとても食えず、火を起こそうにもマッチは無く、窮した末に考え付いたのがレンズで火を起こすことだった。しかしレンズなど何処に有るのだ。双眼鏡でも有ればそのレンズが使えるのだが、ハタと気付いた。車のヘッドライトが使える。早速米軍の車両から頂戴して火起こしに取り掛かった。布切れをよじって火縄を作り、太陽の光を火縄に集めるとポッと煙が立った。苦労して点けた種火を絶やさぬようにして夜間、洞窟の中で煮炊きをした。海水と火があれば何とか生きて行ける目算が付いた。しかし、またもや我が身のこの姿の情けなさ、哀れなこの姿、どうして皆と、戦友と共に死ねなかったのか、臆病なのか、度胸が無いのか、悲しくなった。その時の海水の不味さが今でも思い出される。
武ちゃん
それからの食糧探しは大変だった。米軍基地の近くまで遠出しなければ残飯にありつけなかった。玉砕後何カ月位経ってか分からないが、サツマイモの菜っぱを取りにカロリナスの台上に行った時、名古屋出身の武ちゃん(故武下氏)と言う陸軍の敗残兵と会い、意気投合して行動を共にすることにした。昼間、山芋の太めのを掘り当て、米軍の缶詰の缶に釘で穴を開けて擦り下ろし、内地の正月のお供え餅そっくりに、こってりと見事に出来上がり、皆で喜んで食べた。翌朝は米軍の作ったトウモロコシ畑の繁った所に入り込んで寝入ってしまった。
私はどうも寝つかれず、朝になり辺りが明るくなると、どうも様子がおかしい、それもその筈、日本兵の白骨や防毒面、水筒、その他が大型機械で耕起され、その辺り一面白骨の山となっているではないか。付近が騒がしくなったので身動きせずにじっとしていると、「ガサッ。」と音がして「ガチャッ。」という音と同時に、武ちゃんが「ギャッ。」という声をあげると前のめりに倒れ、そのまま動かなくなってしまった。見ると、後方に米兵が二名位立っているではないか。とっさの出来事であった。前夜に食べた山芋のお返しに武ちゃんが何度か大きな屁をしたので、それが米兵に聞こえてしまい、畑の中に入ってきて日本の敗残兵を見つけ、小銃で背後から狙い撃ちされたのだった。仲良しの武ちゃんは先に逝ってしまった。
その後二晩、小さな芋を見つけては小さな皿に盛り、武ちゃんに供えに行った。遺体は米軍が丁寧に土を掛け、盛り上げてあったが、三日目の晩にはもう遺体を掘り起こして、跡形もなかった。名古屋の武ちゃんとも別れ、またねぐらを探してカロリナスを移動しつつ、月日が経って二十年も春となった。もうこの頃は高野と二人っきりの時も多かった。
生ける亡霊
「太平洋の防波堤」も敢えなく崩れさり、我々兵士に情報は全く伝わらず、まだ残っているであろう連合艦隊がサイパン、テニアンを奪回に来るだろうというかすかな望みも、もはや断念せねばならぬ時期らしい。その予感がしつつある。
生き残ってしまった我が身をもてあまし、敗残の身を生ける亡霊が如くカロリナスの薄暗いジャングルににさまよわせる姿にはかつての輝かしい皇軍兵士としての面影は既に無く、身に帯びるのは自決用の手榴弾ひとつ。『このテニアンの地に二十三才の身を野ざらしにするのか』、『誰にも知られぬ所で』。
でも高野がいる。生死の境を共にしてきた高野がいる。高野がいなければとうに自決していたかも知れぬ。
高野の再々負傷
ある日、二人で西海岸へ行った時、高野が負傷してしまった。
米軍機の爆撃の跡の大きな穴に我々が潜んでいた時、米兵に狙い撃ちされてしまったのだ。高野は以前にも胸に創傷を負っていたために苦しくて長く伏せていることが出来ず、我慢しきれず体を上げたところをトラックの上から狙撃されてしまったのだ。
銃弾は右鎖骨を貫通しており、血止めをするのがやっとで今度は大変だった。これまでも二度三度と重傷を負ったにも拘らず、またしても重傷を負ってしまったのだ。『高野、死ぬなよ。生きていてくれ。死ぬときは二人で。』と念じながら、寄り添って米軍の帰るのを待ち、夜が来てから彼を支えて歩き出した。『しかし、この小さな島テニアンに生きる場所があるのか。島全部がアメリカだ。』『いや、まだ日本は敗れていないのだ。一日でも生き延びよう。』『自決用の手榴弾はある。米軍に撃たれたら、この手榴弾で自決しよう』『いや、今となっては自決も出来ない。』と何度思い、何度考え直したろう。皆が立派に戦死したのに、自分はなぜ死ねぬのか。戦友達と死に別れてから早くも六、七カ月が過ぎようとしている。日本内地はどうなったろう。母は元気だろうか。上海から帰っても家には寄れず、横須賀で急ごしらえの隊編成、そして出航、米潜水艦との出会い、やっとテニアンへ、大砲の陸揚げ、米艦との撃ち合い、自分は今後どうすれば良いのか。米兵に撃たれるのを待つのか。頭の中を想いが渦巻く。重傷の高野をどうしたらいいのか。
ボロボロの敗残兵
日本ヤシの小川隊本部兵舎にいる時分、同郷の久留生上水と食事を分け合って食べ合っていた頃を思い出した。しかし、今はだれもいない。どこにもいない。米軍の艦砲にやられたのか。サイパンからの長距離砲にやられたのか。アメリカの飛行機にやられたのか。現在生きているのが不思議な位なのだ。同じ仲間に敗残兵をしていた名古屋の武ちゃんも、南海岸で海を泳いで遠くへ流されてしまった兵隊も、我々の洞窟の隣の小さな洞窟にいた二人も撃たれて死んでいる。
だんだん心細くなってくる。生きて日本へは帰れないのだ。一年でも二年でも日本の軍隊の教育を受けた者としては。だが、今の敗残兵の姿はどうだ。ボロボロの陸戦隊の服は着ているのだが、上衣は縫い目だけしか残っていない部分もあり、ズボンは下の方が全然切れてない細い針金で糸の替わりに縫い合わせて着ているのだ。年輩の兵隊はヒゲぼうぼうの延び放題。まるで山賊の集団だ。
今の敗残兵仲間ではテニアンの地理に詳しい者、あるいは食糧を確保できる者が指揮者なのだ。だが、玉砕して大家司令と別れてから早や七ヶ月以上経っている。米軍はテニアンの日本の飛行場を整備してB29式爆撃機を並べている。硫黄島か日本本土近くまで行って来る様な気配であった。
後日判ったことなのだが、大家司令が大変心配なされていたテニアン在住の民間人の人々のうち、テニアンのバンザイ岬に身を投げた人々も沢山いたらしいが、生き残った者は米軍に収容され、傷の手当てをしてもらい、元気を取り戻しているようだった。地下の大家司令に報告したいものである。
米軍放送
この頃になると、米軍が拡声器で「戦争は終わりました。日本の兵隊さん出て来なさい。」と大声で怒鳴る日が毎日のようにあった。「水もあります。煙草もあります。アメリカは決して皆さんを殺さない。」と聞こえてくる。
だが、B29爆撃機の編隊が毎日サイパン・グァムからも飛来し、テニアンの上空で編隊を組み、西の方に飛んでいくのだ。戦争が終わったはずがない。しかし、日本海軍の大高少尉が毎日のように米軍と共に来て、「敗残兵の皆さん、早く出てきなさい。そして疲弊した日本に帰り、日本の再建のために尽くすのだ。お前達の力が必要なのだ。」と繰り返し放送する日が続く。それでも我々には信用出来ない。まだ降伏は出来ない。
毎夜、我々は交代で米軍兵舎の近くに食糧を探しに出掛けていった。米軍は、食糧や缶詰の食べ残しに油をかけて崖の上からダンプで落とすのだ。うじ虫のいっぱい付いている缶詰等を拾い集めて蓄えておき、長期の敗残兵生活に備えた。
カッチ工場
二本ヤシ柴田砲台下の海岸寄りにカッチ工場という、南洋の潅木を利用した染め物の染色料を作る工場があった。その付近に日本の敗残兵がおり、集会所らしき場所もあり、玉砕前か直後に第一航空艦司令長官の角田中将も来たらしい。と言うような話が敗残兵仲間より聞かれたが、その後、角田長官の姿を見ることは無かったという。最後の「一航艦」司令部の深い、一番下の洞窟内で拳銃で自決されたものと思われる。日本の潜水艦が長官を救出に浮上したという海上の近くである。後に知ったところでは、サイパン陥落の報を受け取った日本軍部はテニアンの航空隊の全滅を恐れてダバオに移動を命じたが、数度の潜水艦での救出計画は米艦船に発見されて失敗に終わったという。
カッチ工場付近は初めての我々には勝手が分からず、夜のみ二度ほど近付いたが、それくらいでは全く見当も付かなかった。
食糧
カロリナスの我々の隠れ家の洞窟の西側にかなり大きな洞窟があり、満州から派遣された陸軍の敗残兵がいた。ある日、カロリナス崖下でその洞窟の誰かが、島内に僅かに残った牛の一頭を拳銃で撃ち殺し、味噌漬にして食べたのだが、食べ過ぎた下士官が下痢をしてしまった。ところが洞窟内では用が足せず、かといって洞窟の外に出ると米兵が崖の上から機関銃で狙っているのだ。夜ならば洞窟の外でも用が足せるが、なにせ下痢は夜まで待ってはくれない。にっちもさっちも行かなくなったその下士官が洞窟内で拳銃を乱射し、敗残兵同士の争いが始まり、危険な状況だったらしいことを後で知った。
我々も米軍の目を盗み、焼けた民家の石垣に生えている内地のニラに似た青物を二、三人で採り、米軍の缶詰の空き缶に入れて海水で煮て食べたことがあったが、これが失敗だった。葉だけ食べた者は大したことは無かったが、汁まで全部飲んでしまった者は災難だった。血が混じるほどの猛烈な吐き気で大変苦しい思いをした。
住吉神社の付近で一本だけ焼け残ったパンの木の大木に実がなっていた。大きそうな実をもぎ採って焼いて食べたのだが、これがなかなかうまい。敗残兵となってから今までに食べた果物では一番美味であった。パパイヤの木も殆ど焼け、実が全くついていない。パパイヤの青い実は刻んで漬け物にすると結構食べられるのだ。しかし、今ではどこにも実がない。ソンソンの町のあたりは草も無いほどの焼け野原なのだ。我々敗残兵が何とか生きていけるのはカロリナスの一部、それも崖沿いのほんの僅かな土地のみである。
南洋の常夏の気候のもと、身につけている物と言えばボロボロになった服とも言えない物であり、食べる物と言えば芋やカタツムリ、米軍の残飯であり、我々敗残兵にとって季節感などと言うものは無縁であった。
この頃、テニアンで原爆の組み立て工場ができたらしいが、我々には知る由もなかった。
投降
おそらくこの年が我々の最期の年となるだろう。誰にも知られずに朽ち果てていく二十三歳の短い命。しかし、大東亜戦初期より現在まで大勢の若い命が消えていっているのだ。もう少し生きよう、最期は米軍に胸を撃ってもらって死のう。この頃になると手榴弾で自決する事は考えなくなっていた。手榴弾の安全栓は錆びて動かなくなり、木の小枝と取り替えた者もいた。
最初カロリナス海岸洞窟にいた我々は今井兵曹とも別れ、北方のキスカ島より撤退してテニアンに派遣された安浦兵長と中村先任と高野電信員と清水一水と私というグループになっていた。
食糧探しも仲々大変になってきていた。米軍のゴミ捨て場がカロリナスの西方、敗残兵の足でも三十分位で行き着ける場所にあることが分かり、交代でごみ捨て場に食糧を探しに行くようになった。残飯や牛肉や他の食糧の残りをダンプで運び、高台から落として油をかけて焼くのだが、下から上へと探しながら登ると結構良い品物や食糧が土嚢の半分くらいは拾えた。早速山へ帰って皆と喜び合って食べ、幾日かが過ぎていった。
相変わらず早朝よりB29爆撃機が西方へ向かって編隊を組んで飛び立っていく。ゴミ捨て場で拾ったアメリカの雑誌「ライフ」を見ると、日本本土を爆撃しているらしく、写真に日本の都市が写っているではないか。米軍は、硫黄島や沖縄を攻撃し、硫黄島をも占領したのであろうか。ただ声もなく驚くばかり。中村先任は多少英語が分かるらしく、所々読んでいる様子であった。それでも日本が敗れるとは誰も思わず、相変わらずゴミ捨て場に通っていた。
数日後、私他二名でごみ捨て場に残飯拾いに出掛け、焼け残りの缶詰や豚の足や野菜の缶詰等、真新しい品々が袋一杯収穫があり、喜び勇んで帰ろうとした時のことであった。誰かが大きな缶を踏み、転がして大きな音を立ててしまったのだ。突然、上からまぶしい投光器の光を照射され、腹這いの状態でじっと身動き出来ないでいた。すると、上から日本語で「日本兵だろう。私は、海軍の大高分隊士である。もう戦争は終わったのだ。上に上がれ。逃げても無駄だ。」と言われた。日本海軍の将校が言うのに間違い無いだろうと一応観念し、言われるままに上に登ると、何と米軍のジープと米軍の将校らしい数名の者と先ほどの大高分隊士が居るではないか。他に日本人らしい者も見られた。遭難者のような我々敗残兵とは大違いの健康的な体格に戻り、こざっぱりした服も着ているのだった。
我々が呆気に取られていると、米兵がさっと椅子を出し、「プリーズ。どうぞ。」と言う。進められるまま椅子に座りはしたが、山に残してきた中村先任達の事を思うと、どうしても山に帰りたいので、大高分隊士にまだ仲間が山にいることを告げた。大高分隊士は米軍の兵士に何やら話していたが、米兵に命じて箱にサンドイッチを八名分くらい詰めさせ、我々三名の敗残兵に「これを持って直ぐに来た道を間違わずに山に戻れ。もし道に迷うと米軍に撃たれる。」など、細かい注意を受けた。
夜の明けない内にもと来た道を仲間の待つ山に帰った。中村先任等の敗残兵達は、我々食糧探しの者の帰りがあまりにも遅いため何事か起きたと予感し、これからの行動を相談し移動の準備をしていた。我々が事の次第を説明をすると、中村先任は「まだ、B29が西へ飛んでいる。戦争は終わってはいない。例え戦争が終わっても、我々軍人は投降は出来ない。」と言うので、『この山を出よう。』と一同の相談が決まり、移動の準備を始めた。
もう東の空は明け始めていた。何時間か経つと山の下が騒がしくなってきた。そっと覗いて見ると、なんと下には米軍の救急車やジープが止まっているではないか。拡声器をこちらに向けて、「迎えに来ました。どうぞ、下に降りて下さい。」と言う。我々も、もう是れ迄と観念した。
中村先任はヒゲぼうぼう。高野は針金で繕ったぼろぼろの上衣。ズボンはとっくに無くなり、代わりに紐の代用として米軍の電話線で土嚢の麻袋を縛って後ろに垂らしていた。前の方は無くとも、後ろが有れば腰を下ろした時あまり痛くない。後ろだけで結構用が足りた。その姿で、中村先任を先頭に一同山を降りた。
待っていた米軍と大高分隊士達は、車からタバコを出して我々敗残兵に手渡してくれた。終戦間近になって、やっと投降したのだった。
捕虜収容所に入っても、陸軍の戦死した方々、第五十六警備隊の方々を思うと、米軍給与の食事も喉を通らぬ日々が続きました。米軍上陸地点で正面から迎え撃った陸軍の麻生隊と海軍の及川隊は全滅し、両隊の生存者は一人も確認出来ませんでした。米軍上陸地点付近、特に陸軍麻生隊と海軍及川砲台全員、陸軍五十連隊の一部の遺体約三百体は後日、上陸地点の正面で掘り出され、日本に帰りました。麻生隊のトーチカにも七体あり、同じく収容されました。
警備隊のうち、小川隊の沼田砲台もアシーガー近くでサイパンの米上陸用支援艦に対して援護射撃を行い、米艦に被害を与えたが、サイパンよりの米軍の何十門、何百門という一斉射撃によって、また、空からの爆撃によって破壊され、かろうじて生き残った隊員もカロリナスで自決して果て、生存者は一人もいませんでした。
おかしな話
昭和二十年、春もとうに過ぎた七月も中旬の頃、捕虜収容所で不可思議な事件が起きた。
収容所内の我々の仲間に渡辺一曹という猛者がいた。彼とは敗残兵生活を倶にし、投降も一緒だった。堂々たる体格の持主で、横須賀海兵団に居た頃は相撲部に所属していたらしく、格闘技には自信があるようであった。
彼が第五十六警備隊小川隊の何番砲かは忘れてしまったが、二本ヤシ柴田砲台の射手をしていたころ、米巡洋艦と一騎打ちをやってのけたほどの大変な猛者だった。額と肩に負傷しており、後に脚にも傷を負ったが彼の猛者ぶりは一向衰えず、中村先任下士官と数回口論もし、日本刀で切合いに及ぶ場面もあった。
中村先任下士も剣道の達人で、どちらも後へは引かない同士で我々兵は本当に困った。この頃は兵とか下士官とか階級は意味が無くなっており、皆同じ気持ちになっていたのに何故か気の合わない二人なのであった。
投降して収容所に入っても渡辺一曹は何故か落ち着かず、数日経って米軍将校にトンでもないことを掛け合った。「やっぱり山へ帰してくれ」と言う。その米軍将校はシュナイダー大尉かエイプ少佐だったと思われるが、彼等の困惑した顔が目に見えるようだ。しかし彼等の取った処置はもっとトンでもないものだった。なんと、彼の言い分を請け容れてしまったのだ。
ある雨の降る夜、エイプ少佐は彼の頭から雨カッパを被せて作業員に見せかけ、トラックに乗せて山へ向かい、無事にカロリナス台近くまで送り届けたという。その時にエイプ少佐の言うよう、「また気が変わったなら米軍に投降するように」と。食糧を渡してジャングルに消える彼の姿を見送ったという。
後でこの話を聞き、例え勝ち戦とは言え米軍将校のなんと度量の大きいことかと心中驚きもし、日本軍に同じ事が出来るだろうかと考えさせられもした。
サイパン戦では何千名という米将兵が戦死し、テニアン戦に於いても同様の戦死者が出たというのに、米軍のこのような行動は我々収容所仲間にも大変な驚きをもって受けとめられた。
山に帰った渡辺一曹はその後数日して再び投降してきたのだが、一体何のために山へ帰ったのか我々にはついに理解できなかった。彼は内地へ帰って間もなく亡くなったという。
シュナイダー大尉
米軍の将校についてはこんな逸話もある。
投降して収容所にいた我々の前に一人の将校が現れ、日本語で話しかけてきた。それも流暢な東京弁でいきなり、「お前達、ヤンキーに負けたな」と話しかけてきた。面食らっている我々に彼は親しげに話しかけた。彼はシュナイダー大尉と言い、東京で生まれ、東京で育ち、東京の大学まで出ていると言う。道理で日本語が達者なはずだ。彼は終始暖かく我々に接してくれたのだが、ある日彼に難問が降り掛かった。B29の機長として東京を空襲せよという。
彼はその命令を拒否してしまった。自分が生まれ育った街を自分の手で焼き払うのは彼には出来ることではなかった。米軍では命令に逆らうと階級を下げられ、給料も下げられてしまい、彼も二階級下げられ少尉になってしまったが甘んじてそれを享け容れたのである。米軍の将校の給料で二階級下げられると云えば相当な金額でしかもアメリカでは給料が下がるとすぐ奥さんに離婚されてしまうと言う話だが、シュナイダー大尉はただ笑っているだけだった。アメリカの軍人にも偉い人がいるものだと今更乍ら考えさせられた。
捕虜収容所で暫く過ごした後、サイパンを経由、ハワイで傷の手当を受けることになった。
虜囚
昭和二十年八月、我々捕虜はサイパンのドンニー収容所に移送され、さらにハワイに送られる事になった。ハワイに移送される船上で戦争の終わった事を知らされた。
ハワイのオワフ島のホノルル港に入港すると、そこには大勢のアメリカ婦人が出迎えていた。勿論、歓迎では無かった。我々が下船すると彼女等は口々にジャップ、ジャップと我々をののしり、唾を吐き掛ける者もいた。先の尖った靴で蹴飛ばされた者もあった。それもその筈、彼女等は未亡人らしく、「ユー、サイパン」、「ユー、テニアン」と我々に聞いてくるのだ。我々は彼女達の仇であった。
ホノルルの建物は皆、日本軍機の銃撃で穴だらけになっており、その上にペンキを塗って弾痕に丸く印を付けていた。真珠湾攻撃時の日本軍機の攻撃の凄さをまざまざと見せつけられた思いがした。
ハワイでは暫く医者の治療を受け、頭に残ったままになっていた銃弾かリーフの破片を摘出して貰った。治療が終わるとまた船に乗せられ、アメリカ本土に移された。カナダの国境近くのシアトルに上陸し、汽車で太平洋岸を南下、サンフランシスコ湾内のエンジェリー島収容所に収容された。ここではパンのみの食事であった。暫くしてまた汽車に乗せられ、今度は内陸部のテキサスの収容所に移された。
テキサスの収容所にはドイツの兵隊も大勢収容されていた。彼等は皆、収容所の外で元気に働いており、夕刻になると早めに収容所に帰って来ると我々日本兵に英語で話し掛けてくる。「我々ドイツ兵は一生懸命に働いて金を貯め、国へ帰って元のドイツにするのだ」と言う。時には我々のテントにスピーカーを向けて音楽等を聞かせて呉れる事もあった。同じ敗戦国の兵隊でも我々日本兵はあまり作業にも出ず、米兵が英語を教えようとしても誰も習おうとはせず、これからは英語が世界の共通語になる等と我々を説得しても耳を貸す者はいなかった。我々はあまりにも世界情勢に無知であった。今にしてドイツ人達を見習えば良かったと悔やまれる。間もなくドイツ兵は帰国し、我々もまた汽車でロッキー山脈を越え、シアトルより船で帰国する事になった。
我々はアメリカ本土を彼方此方と移動させられた。そして見た物は方々に積み上げられた鉄屑の山だった。何と資源の有る国は大した物だと感心させられた。広大な国土の割に人工が少ないせいなのだろうか、鉄道の駅員は皆老人か婦人が多いのにも驚かされた。大きな駅に停車すると子供達が集まってきて口々に「シュガー、シュガー」と言いながら手を出してくる。砂糖が不足しているらしい。汽車の中で支給される缶詰の中のコーヒー用の角砂糖だけを取り上げて昇降口から掃き出してしまう。子供達はそれを拾いに集まって来るのだ。アメリカでは男手が少なく、資源はあってもそれを生産する労働力が足りないらしい。
帰還
心ならずも生き延びて虜囚の辱めを受ける身となった我々はこのまま日本に帰還するのを潔しとはしなかった。アメリカ国内を汽車で転々と移動する都度、我々をブラジルに送って呉れぬかとアメリカ兵に頼んだが受け入れては貰えなかった。「お前達は大事な送還者なのだ。一旦、日本へ帰ってから出直して来なさい。」と言われた。
昭和二十一年二月、洋上より富士山を見、九里浜に上陸。二度と踏めぬと想い続けていた内地の土を踏んだ。
帰国してからも亡き戦友を想わぬ日は一日とて無かった。空を見てはテニアンの空を想い、川面を見てはテニアンの海を想う。食事の度に心に涙し、一杯の水に胸を熱くするものがあった。タバコを止め、酒も控えてひたすら戦友の御霊に祈る。心に熱く焼き付けられた十字架を抱きつ。
昭和五十一年、今は亡き各隊々長の奥様方の御臨席の元、拙宅にて三十三回忌法要を執り行う事が出来た。出家していた長男も檀那寺御住と共に回向を手向けて呉れた。平成四年、念願であった慰霊碑を建立。平成五年、五十回忌慰霊祭を挙行。
想うこと
「敵に勝つ為には敵を知れ。」米軍はこの言葉を常に口にしていた。今にして思えば先の戦争はこの言葉通りに終始していた。米軍は日本の暗号を解読し、日本軍の機先を制したのみならず、日本の国情をも熟知していた。日本の占領計画さえ立案されていたという。日本は戦う前に負けていたのだ。日本を、日本人を研究し尽くしたアメリカに比べ、日本は国民の耳目に蓋をし、精神論のみを振りかざして立ち向かった。無謀と言うも愚かであった。その愚かさが国民を塗炭の苦しみに追いやったのだ。物量に於いてもそうだった。資源の豊富なアメリカに比較し、南方方面に広く薄く手を広げ、少しづつでも資源を確保しながら戦争を遂行するという方法は綱渡り的でさえあった。最前線に戦力を集中し、後方は武器弾薬も乏しく、卵のように殻を割られてしまえば中は脆弱なばかりであった。その脆弱な白身がテニアンであった。
昭和十九年二月の空襲時まではテニアンの飛行場には常時八百機から九百機の飛行機が駐機していた。しかし、次々と来襲する米軍機の前に次第に少なくなっていった。搭乗員も不足し、訓練途中のやっと飛行機を飛ばせるようになったばかりの彼等も米機動部隊の攻撃に飛び立って行ったまま帰るものは無く、米軍上陸時には只の一機も見られなかった。
陸軍に配属された十両の戦車にしても而り。米戦車の三分の一の装甲しか無く、米軍歩兵の携帯するバズーカ砲で簡単に破壊されてしまう有り様だった。
海軍の海岸要塞砲にしても十五糎法は日露戦争当時、東郷平八郎連合艦隊司令長官の旗艦「三笠」の主砲と同じ旧式のアン式砲で、大正の初期の製造であった。三年式十二糎砲も同様に古い物だった。米軍の軍艦の大砲は殆どの艦が自動ベルトコンベアーを装備し、艦の弾薬庫より砲まで砲弾が自動的に送られていた。我々は自分の手で砲弾を運び、手で砲身に込めていたのだ。我々の砲が一発発射する間に米艦はボタン一つで十二門の砲が一斉に火を吹くという電令発射装置さえ備えていたのだ。蟷螂の斧とは我々の事だった。
兵卒の持つ小銃でも、我々の物は五発込めで一発づつしか発射出来なかった旧式な銃であった。彼等のは自動小銃であり、最低でも八連発可能な銃を歩兵の誰もが持っていた。我々が一発打つと彼等は八発は撃ち返せるのである。彼我の差は何倍もあったのだ。
テニアン守備隊の上層部、特に第一航空艦隊・角田司令長官や陸軍の五十連隊・緒方連隊長と海軍の大家司令、陸海空の各隊長級、また戦争経験のある古参の下士官等はこの戦争の行方は大体わかっていたような気もするが、我々兵は立派に戦死すれば日本はこの戦争に勝つという迷信にも似た信念を持っており、玉砕という美名に自分から酔っていたのだ。全兵員が気力のみ、精神力のみで戦っていた。
敗戦、復興、成長、経済大国となった現在の日本の姿。この姿を見る事無く散って逝った若者達。平和な日本、繁栄する日本を望んでいた彼等。太平洋の防波堤となるべく我が身を挺した軍人、軍属、民間人の方々。果たして日本はあなた方の望んだ通りになったでしょうか。瞑目し、御霊の平安を祈るのみ。